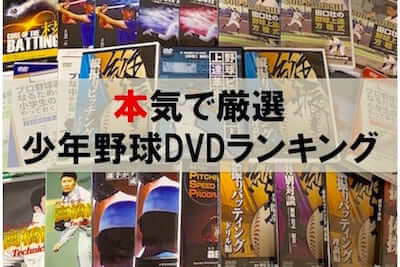【簡単実例】ピッチャーにセーブがつく条件とホールドとの違い
プロ野球の試合結果を見ると勝ち投手・負け投手以外にS(セーブ)がつく投手がいます。
今回、投手にセーブポイントがつく条件とセーブとよく似たホールドポイントとの違いについて解説しています。

プロ野球の投手成績を見るとSマークがついている選手がいますが、このマーク気になりますよね?
このSはセーブといい、おもに試合終盤に登場する抑え投手につくのですが、セーブがつくためにはいくつかの条件があります。
今回は
- ピッチャーにセーブがつく条件
- セーブがつくときとつかないときの実例紹介
- セーブとホールドポイントの違い
について説明していきます。
芹田祐(セリタタスク)
理学療法士として整形外科病院・整形外科クリニックなどに10年ほど勤務。野球現場では小学生からプロ野球まで幅広い年代の選手に対して述べ1000名以上のリハビリテーション・トレーニング指導経験あり。
保有資格
理学療法士/認定理学療法士/JARTA認定トレーナー/国際認定シュロスセラピスト/修士(医科学)
この記事の目次
セーブがつく条件

プロ野球を運営している日本野球機構のホームページにはセーブがつく条件はこのように書かれています。
次の4項目をすべて満たした投手にはセーブの記録を与える
引用:公認野球規則|日本野球機構
その4項目の解説を分かりやすく説明するとこんな感じです。
- 自分のチームが勝った試合で最後に投げていた選手
- 勝ち投手の記録がついていない
- 最低1/3回の投球回を投げた選手
- 次のどれかに該当すればOK
・3点以内のリードで登板して最低1イニングを投げた場合
・相手ランナーがいる場面で登板して抑えたとき。(変わって2人目のバッターまでが得点したら同点に追いつかれるとき)
・最低3イニング投げた場合

条件1の自分のチームが勝った試合で最後に投げていた選手は分かりやすいですね。
条件3の最低1/3回というのは相手のバッターを1人打ち取ればOKです。
条件4が少しややこしいですが、どれかの条件を満たせばセーブの権利を手に入れることができます。
ではこれから実際にセーブがつく例とつかない例を見てましょう。
セーブがつく例とつかない例

【5対2の9回に登板して0点に抑えて勝利】
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
| 自分 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件1〜3を満たして条件4:3点リードで登板して最低1イニングを投げた場合に該当するのでセーブがつきます。
このケースが1プロ野球でセーブがつく場面で最も多いです。
【7対1の7回から登板して5点とられて勝利】
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
| 自分 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
条件1〜3の条件を満たして条件4:最低3イニングを投げた場合に該当するのでセーブがつきます。
3点以内の場面で登板しないとセーブがつかないと思っている方が多いですが、このケースでもセーブになります。
ただ、プロ野球でセーブがつく抑え投手が3回投げることはほとんどないので、この条件が適用されることは少ないです。
【1対0の9回に登板して1点とられたが10回をおさえて勝利】
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | |
| 自分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 相手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
試合に勝利して最後に投げていたのでセーブがつきそうですが、このケースはつかない可能性が高いです。
理由は勝ち投手になってしまうかもしれないからです。
勝ち投手というのは、決勝点を上げたときに投げていたピッチャーにつくのが大前提です。
このケースの決勝点は10回表に挙げた1点なのでそのときに投げていた抑えピッチャーに勝ち星がつく可能性があります。

勝ち星がつくとセーブはつかないので、この事例ではセーブがつかなくなります。
ただ、こういった難しいケースの場合、勝ち投手は公式記録員によって決定されることになっています。
このあたりの詳しい話が気になるかたは下の日本野球機構のコラムを参考にしてください。
セーブとホールドポイントの違い

プロ野球での投手の役割を大まかに分けると
- 先発投手
- 中継ぎ投手(セットアッパー)
- 抑え投手(クローザー)
この3つに分けられます。
先発投手ができるだけ長いイニングを投げて試合を作り、中継ぎ投手がリードを守り、抑え投手が最終回である9回の相手攻撃を抑えて勝つというのがセオリーです。

先発投手→勝ち星
抑え投手→セーブ数
この数字を見ればどれだけ自分の役割を果たしているのかが分かりやすいです。
一方、中継ぎ投手はチームへの貢献度がみえにくいという問題点がありました。
そこで、中継ぎ投手を評価する指標として作られたのがホールドポイントです。
最近では、試合結果で勝ち星やセーブ以外にホールドポイント(HP)も見かけのではないでしょうか。
ホールドポイントがつく大まかな条件は下の通りです。
- 先発投手、勝利投手、敗戦投手、セーブ投手のどれもに該当しない
- 試合の最後に投げていたピッチャーではない
- 1アウト以上をとる
- ランナーを残してマウンドを降りたあと、そのランナーが同点または逆転の走者としてホームインしていない
中継ぎ投手は年間で登板する試合が多いにも関わらず、球団からの評価が低く、年俸が上がりくいといわれていました。
そういった問題を解決するために2005年からホールドポイントが1番多い選手には最優秀中継ぎ投手のタイトルができました。

活躍度合いを表す数値があればみなさんにも分かりやすいですよね。
ちなみに、2020年のセーブとホールドポイントの上位5選手は以下の通りです。
 <セリーグ> (Sはセーブ、HPはホールドポイント)
<セリーグ> (Sはセーブ、HPはホールドポイント)
| 順位 | 選手名 | S | 選手名 | HP |
| 1 | スアレス (阪神) | 25 | 祖父江大輔 (中日) | 30 |
| 2 | マルティネス (中日) | 21 | 清水昇 (ヤクルト) | 30 |
| 3 | 石山泰稚 (ヤクルト) | 20 | 福敬登 (中日) | 30 |
| 4 | フランスア (広島) | 19 | マクガフ (ヤクルト) | 27 |
| 5 | 三嶋一輝 (横浜) | 18 | 石田健大 (横浜) | 26 |
※ホールドポイントの1位〜3位は同率1位です。
 <パリーグ>
<パリーグ>
| 順位 | 選手名 | S | 選手名 | HP |
| 1 | 増田達至 (西武) | 33 | モイネロ (福岡) | 40 |
| 2 | 森唯斗 (福岡) | 32 | 平良海馬 (西武) | 34 |
| 3 | 益田直也 (ロッテ) | 31 | 高橋礼 (福岡 | 27 |
| 4 | ブセニッツ (楽天) | 18 | ハーマン (ロッテ) | 26 |
| 5 | ディクソン (オリックス) | 16 | 玉井大翔 (日本ハム) | 25 |
基本的に抑え投手はチームに1人の選手を固定するのが主流です。
そのため、セーブランキングに入っているのは各球団で1人ずつになっています。
一方、中継ぎ投手は試合展開によって色々な選手が登板します。
そのため、中日・ヤクルト・ソフトバンクのように複数の選手がランクインすることがあります。
- セーブは勝ち試合を締める抑え投手につく
- ホールドポイントは試合中盤に登場する中継ぎ投手につく

250セーブで名球会入り

みなさん名球会という言葉をご存知でしょうか?
名球会はプロ野球でものすごい成績を積み重ねた選手のみ入会できる組織です。
いわば一流の中の一流の証です。
数多くのプロ野球選手がいる中で現在の会員数は投手16名、野手が48名しかいません。
名球会に入ることができる条件はこちらです。
- 投手として通算200勝利以上
- 投手として通算250セーブ以上
- 打者として通算2000安打以上
※ 通算成績はメジャーの成績も合算される。ただ日本プロ野球での記録を起点。
引用:日本プロ野球名球会オフィシャルサイト
めちゃくちゃハードルが高いです。
現役時代にこの条件をクリアできれば、引退後も名球会の一員として名を連ねることになります。
抑え投手は250セーブを達成すると名球会入りになります。
しかし、この250セーブを達成したのはいままでにたった3人しかいません。

- 岩瀬仁紀投手(通算407セーブ)
元中日 - 高津臣吾投手(通算286セーブ)
元ヤクルトなど - 佐々木主浩投手(通算252セーブ)
元横浜など
緊迫した試合の最終回に登場して相手の攻撃を抑え、セーブを重ねるのはそれだけ難しいことだといえるでしょう。
セーブがつく条件を知ることでプロ野球観戦が楽しくなる
プロ野球でセーブがつく条件について解説してきました。
セーブがつく条件は少し複雑ですが、慣れてしまえば大丈夫です。
抑え投手はセーブがつく条件が整った場面で登板することが多いです。
応援している抑え投手にセーブがつくかをドキドキしながらより一層プロ野球観戦を楽しんでください!
野球技術系のDVDを60本以上買いあさったぼくが選ぶ野球技術向上のDVDランキングです。
【選定基準】
- 技術向上に効果があるのか
- 小・中学生でも取り組みやすいか
- 保護者・指導者にも有益か
- Youtube等の無料ツールにはない情報か
- お金を出して買うほどの価値があるか