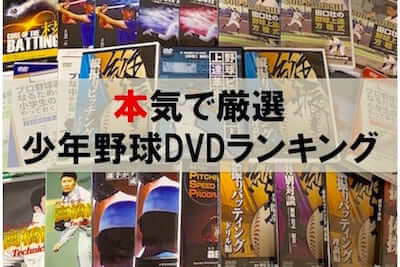野球のコリジョンルールとは?内容や制定の理由・問題点を徹底深堀り解説
野球にできた新しいルールの1つにコリジョンルールがあります。この記事ではコリジョンルールをよく知らない方のためにルールの詳細やなぜ制定されたのかを説明しています。
野球はルールが非常に多いスポーツとして有名です。野球のルールの中には昔からあったものばかりではなく、近年になって追加されたものもあります。
その一つが「コリジョンルール」です。

コリジョンルールとはなに?
先に結論をいうとコリジョンルールは本塁でのランナーと守備の激しい接触を避けるために制定されたルールです。
この記事ではコリジョンルールを以下の3パートに分けて徹底解説していきます。
- コリジョンルールの詳しいルール
- コリジョンルールが出きた理由
- コリジョンルールによる影響と問題点
コリジョンルールのことを正しく知りたい方はぜひご覧ください。
芹田祐(セリタタスク)
理学療法士として整形外科病院・整形外科クリニックなどに10年勤務。野球現場では小学生からプロ野球まで幅広い年代の選手に対して述べ1000名以上のリハビリテーション・トレーニング指導経験あり。
保有資格
理学療法士/認定理学療法士/JARTA認定トレーナー/国際認定シュロスセラピスト/修士(医科学)
この記事の目次
コリジョンルールとは何か
まず、コリジョンルールがどんなルールなのか?を解説していきます。
コリジョンルールは野球における走塁と守備に関するルールです。
具体的には以下のようにルールが規定されています。
- ボールを持っていない守備の選手は、得点しようとしているランナーの走路をブロックしてはいけない
- 得点しようとしている走者が、走路をブロックしていない捕手または野手に接触しようとして走路を外れてはいけない
もう少しかみくだくと
- ボールを持っていないキャッチャーがホームを狙うランナーの進路を妨害したらダメ
- ランナーもキャッチャーにぶつかることを狙って走路を変えたらダメ
ということになります。
この規定を守らずに進路の妨害や走路変更をしたときにコリジョンルールが適用されます。
ただし、外野からの送球がそれてしまい、キャッチャーがそのボールを捕球するために止む無くランナーの走路上に入った(故意でない)場合はコリジョンルールは適用されません。

「故意」であるかがポイント
上の映像はプロ野球でコリジョンルールが適用されたシーンを集めたものです。
コリジョンルールに違反したらどうなるか
次にコリジョンルールに違反した場合はどうなるかを説明していきます。
ランナーが違反したときと守備側が違反したときで対応が変わります。
- そのランナーはアウト
- 他のランナーは元の塁に戻る(ボールデット)
- 2回違反すると退場
- ランナーはセーフで1点入る
- 3回違反すると退場
コリジョンルールの対象となりやすいキャッチャーはベンチ入りしている人数が少なく、替えがききにくいポジションです。
そのため、退場までの違反回数はキャッチャーの方が1回多くなっています。
ただし、審判に悪質な違反と判断された場合はランナー・キャッチャーともに一発退場の可能性がありますので注意が必要です。
コリジョンルールが制定された理由とは
次はコリジョンルールがいつどんな理由で制定されたのかを説明します。
コリジョンルールは2014年にメジャーリーグで初めて制定され、NPB(日本野球機構)では2016年に導入されました。
コリジョンルールがメジャーリーグで制定されることになった背景を紹介します。
2011年にサンフランシスコ・ジャイアンツのバスター・ポージー捕手がクロスプレーで左足首の大ケガをしました。
それ以外にも、同じ年にハンベルト・キンテーロ選手、前年にはカルロス・サンタナ選手やジョン・ベイカー選手、ブレッド・ヘイズ選手など多くのキャッチャーがランナーとの激しい接触によってケガをして長期離脱してしまいました。

そんなにたくさん・・・
クロスプレーによるキャッチャーのケガや長期離脱が相次いだことで大きな問題となっていきました。
そのような背景から、選手の安全を守るためにコリジョンルールが制定されました。
コリジョンルールが選手に与える影響

コリジョンルールが導入されたことで各選手がプレー中に注意しないといけない点が変化してきました。
次は、コリジョンルールが与える各選手への影響について解説していきます。
キャッチャーへの影響
コリジョンルールによる影響が最も大きいのはキャッチャーです。
- ホームベースを隠して守れなくなった
- 返球を待つときの位置変更
- ランナーにタッチしにくくなった
- ホームスチールの警戒
1.ホームベースを隠して守れなくなった
コリジョンルールによってキャッチャーはボールを持たない状態で走路に立つことが禁止されました。
そのため、従来のホームベースを隠して守るというプレーが出来なくなっています。
(以前からホームベース全て隠すのは反則です)
2.返球を待つときの位置変更
また、野手からの返球を待っている間に走路やホームの上に立つことも出来なくなりました。
そのため、ホームの前などに立つ必要があり、キャッチャーがボールを持たずに外野手に指示を出すときの位置が変わりました。
3.ランナーにタッチしにくくなった
さらに、コリジョンルールによってキャッチャーは捕球後にランナーにタッチするまでの距離が長くなりました。
そのため、タッチプレーでアウトを取る難易度が高くなっています。
4.ホームスチールの警戒
また、コリジョンルールを利用してランナーがホームスチールをする可能性が高くなりました。
そのため、より三塁ランナーの動きに警戒を強めないといけなくなりました。
このように、キャッチャーのケガを防ぐために制定されたコリジョンルールですが、守備側が不利になってしまう面も多いです。
ピッチャーへの影響

ピッチャーにもコリジョンルールの影響があります。
投手は送球ミスやパスボールなどでホームのベースカバーに入ることが結構あります。
コリジョンルールはランナーとキャッチャーだけではなく、野手全員に適用されているルールです。
そのため、場合によっては投手がコリジョンルールに違反してしまう可能性があります。
そのため、ピッチャーもしっかりとコリジョンルールを熟知してベースカバーの練習をしておく必要があります。
野手への影響
次はコリジョンルールが野手に与える影響についてです。
コリジョンルールによって野手にはより送球の正確さが求められるようになりました。
以前は多少送球がそれてもキャッチャーのブロックでカバーすることができました。
しかし、コリジョンルールによってキャッチャーはボールを持たない状態でランナーの走路をブロックすることはできなくなりました。
そのため、より正確な送球を行わないと捕手の動き出しが遅れ、アウトを取り損ねてしまう可能性が高くなっています。

1つの送球ミスで負けてしまうこともある
また、コリジョンルールはあくまで明確な基準があるわけではなく、審判の判断によって決定します。
そのため、野手の送球がわずかにそれてしまい、キャッチャーが捕球のために止む無く走路に入ってしまったとしても違反を取られてしまう可能性があります。
野手自身がコリジョンルールの違反を受けることはほぼないですが、間接的にコリジョンルールの影響を大きく受けていることになります。
ランナーへの影響
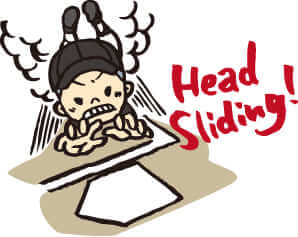
守備側としては気を使う面が多いコリジョンルールですが、ランナーにとってはメリットが多いです。
コリジョンルールによって野手のブロックが禁止されたことで走路を妨害されることなくホームに向かうことができます。

積極的に次の塁を狙えるよ
また、野手がコリジョンルールを気にして体で止めるのではなく手だけでタッチしようとするシーンも増えますので、これをかわしてホームインしやすくなりました。
さらに、成功率は低いですが、以前よりホームスチールを狙いやすくなりました。
コリジョンルールはランナーにとっては概ね有利に働いています。
コリジョンルールの問題点

選手が安全にプレーできるように制定されたコリジョンルールですが、完璧なルールではありません。
次は、コリジョンルールの問題点と課題について紹介していきます。
裁定はあくまで審判のサジ加減による
コリジョンルールの判定を下すのはあくまで人間の審判です。
コリジョンルールを適用する明確な基準があるわけではありません。
そのため、故意ではないブロックや接触に対してコリジョンルールが適用されることもあります。
場合によっては審判の判定に納得がいかず、試合中にモメてしまう可能性があります。

審判も大変だ!!
ルールの穴を突いたプレイが出る可能性あり
次は、コリジョンルールの穴を突いたプレーが行われる可能性についてです。
コリジョンルールの規定では
「ボールを持っていない守備側の選手は、得点しようとしている走者の走路をブロックしてはいけない」
とされていますが、送球がそれてしまった等により、結果的にランナーの進路を妨害してしまった場合は違反になりません。
しかし、これは裏を返せば

わざとボールをそらして送球しよう!!
違反を取られることなくランナーの走路をブロックすることが出来ると解釈することもできます。
もし、こうしたコリジョンルールの穴を突いたプレーが頻発するようになると、もはやルールの意味がなくなってしまいます。
危険なプレイを容認する一因になる可能性
コリジョンルールでは先程もお伝えした通り、理論上は送球をそらすことでランナーの走路をブロックすることが可能になってしまいます。
ではそんな時にランナーはどうするのか?というと
「あえてキャッチャーに力いっぱいぶつかる」
という選択肢が生まれてしまう危険性があります。

そんなことしたらダメだよ!!
というのも、コリジョンルールでは捕手がランナーの走路上にいた場合、ランナーが捕手に接触してはいけないという旨の記載はありません。
このような解釈は危険なプレーを容認する一因となり、コリジョンルールが制定された意義が失われてしまいます。
以上のように、コリジョンルールは選手が安全にプレーするために生まれたルールですが、まだまだ不完全な要素があります。今後はより明確な基準の設定などが求められます。
野球コリジョンルールをしっかり覚えてフェアプレーをしよう
今回はコリジョンルールについてご紹介させていただきました。
コリジョンルールは選手の安全なプレイを促すために制定されたルールですが、守備側としては気を使う面が多く、逆にランナーにとっては有利に働くことが多いというのが実情です。
- コリジョンルールを適用するかは審判の判断に委ねられる
- 解釈によっては危険なプレーを容認してしまう
このようにコリジョンルールにはまだ改善点の余地があります。今後さらに明確で詳細なルール改定が望まれます。
みなさんもコリジョンルールをしっかりと把握し、フェアプレーを心がけましょう。
野球技術系のDVDを60本以上買いあさったぼくが選ぶ野球技術向上のDVDランキングです。
【選定基準】
- 技術向上に効果があるのか
- 小・中学生でも取り組みやすいか
- 保護者・指導者にも有益か
- Youtube等の無料ツールにはない情報か
- お金を出して買うほどの価値があるか